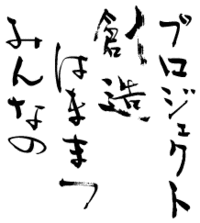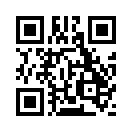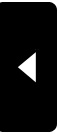› A BloCreation › 出演者インタビュー:藤津亮太さん
› A BloCreation › 出演者インタビュー:藤津亮太さん2013年02月21日
出演者インタビュー:藤津亮太さん
2月24日に控えたA BloCreation企画発表イベント。これを前に、出演者の方々へ今回のイベントへの意気込みや、浜松への思いをインタビューさせていただきました。
今回は第二回目として、イベント司会を担当していただく、アニメ評論家の藤津亮太さんへのインタビューをご紹介します。
藤津さんにはアニメーションと地方という今回のテーマに加えて、プロデューサーという職業のことなどについてもお聞きしました。

■藤津亮太さん
静岡県出身。1968年生まれ。新聞記者、週刊誌編集を経て、アニメ評論家。著書に『チャンネルはいつもアニメ』(NTT出版)など。朝日新聞土曜夕刊コラム「茶話」のアニメ担当のほか、雑誌・WEB・DVDブックレットなど各種媒体で執筆する。毎月第一金曜日夜はニコニコ生放送で「藤津亮太のアニメの門チャンネル」を配信。
・藤津さんは浜松にいたこともあるそうですが、浜松に対する印象や浜松での印象深い事柄はございますか?
藤津さん:僕が浜松にいたのは'94年夏から'97年春までの2年半です。当時僕は、静岡新聞社の記者で、浜松勤務時代は経済担当として河合楽器や浜松ホトニクスを中心に取材していました。流通も担当していたので、西武浜松店の撤退関連を取材したことも印象深いです。
こうした取材を通じて実感したのは、「浜松はものづくりの街である」ということと「しかし、その“もの”とはハードが中心で、ソフトは弱い」ということでした。ですから、今回、こうした企画が浜松で実行されることには少し感慨深いものがあります。
・当イベントでは、受講者は「浜松に関するアニメ企画」という縛りでの企画作りをしていますが、浜松に限らず、藤津さんの考える作品における(制作やコンテンツツーリズム、または単純に舞台として、など広い意味での)地方の持つ重要な要素はなんでしょうか?
藤津さん:日本の大半が「地方」であるのだから、もっと地方が舞台の作品があってもいいはず、とまず思っています。単なる「愛すべき故郷」としてだけでなく、犯罪も含めた事件の現場であることも含めて、もっと地方が舞台になったほうが自然でしょう。
アニメ制作の場合、ネットワークと宅配便の普及で、物理的な距離のデメリットは大幅に減っています。地方を拠点に元請けをするスタジオも着実に増えています。なので、浜松に縁がある人がいれば、浜松にスタジオができてもおかしくない状況だと思います。
「地方の持つ重要な要素」についてですが、作品の舞台としては、「日本に住む多くの人にとって身近な風景」であること、クリエイティブの現場としては、「生活コストが安く、環境がいいこと」があると思います。
・また、当イベントには「地方とアニメーション」という軸の他に「プロデューサー育成事業」という側面もあります。ご職業柄、今まで数多くのプロデューサーの方とお話をされてきたと思いますが、藤津さんの考えるプロデューサー像とはどんなものでしょうか?
藤津さん:「優秀なキャッチャー」です。ボールを投げるのはクリエイター=ピッチャーですが、必要に応じてピッチャーをリードしたり、ワイルドピッチになった時には体を張って受け止める存在。
・ちなみに、藤津さんは当イベントの顧問である赤尾さんとも面識があるようですが、お二人で共通するアニメに対する意見などはあったりするのでしょうか?
藤津さん:赤尾先生とアニメの好みについて語り合ったことがないので不明ですが、赤尾先生のほうが僕よりポップ指向が強く(広く楽しめるエンターテインメント性を重視する)、僕はもうちょっと風変わりな、不思議なテイストの作品を好んでいるのではないか、と勝手に想像しています。
・最後に、このA BloCreationという企画に対してのご意見をお願いいたします。
藤津さん:意義のある企画と思います。一つ付け加えると「PDの考える企画」と「クリエイターの考える企画」の違いが体感できると、もっとよいかなと思いました。
以上、藤津亮太さんへのインタビューでした。
藤津亮太さんもいらっしゃる企画発表イベントの詳細はこちらです。
見学のご応募もこちらのフォームより受け付けておりますので、みなさまぜひご来場ください。
今回は第二回目として、イベント司会を担当していただく、アニメ評論家の藤津亮太さんへのインタビューをご紹介します。
藤津さんにはアニメーションと地方という今回のテーマに加えて、プロデューサーという職業のことなどについてもお聞きしました。

■藤津亮太さん
静岡県出身。1968年生まれ。新聞記者、週刊誌編集を経て、アニメ評論家。著書に『チャンネルはいつもアニメ』(NTT出版)など。朝日新聞土曜夕刊コラム「茶話」のアニメ担当のほか、雑誌・WEB・DVDブックレットなど各種媒体で執筆する。毎月第一金曜日夜はニコニコ生放送で「藤津亮太のアニメの門チャンネル」を配信。
・藤津さんは浜松にいたこともあるそうですが、浜松に対する印象や浜松での印象深い事柄はございますか?
藤津さん:僕が浜松にいたのは'94年夏から'97年春までの2年半です。当時僕は、静岡新聞社の記者で、浜松勤務時代は経済担当として河合楽器や浜松ホトニクスを中心に取材していました。流通も担当していたので、西武浜松店の撤退関連を取材したことも印象深いです。
こうした取材を通じて実感したのは、「浜松はものづくりの街である」ということと「しかし、その“もの”とはハードが中心で、ソフトは弱い」ということでした。ですから、今回、こうした企画が浜松で実行されることには少し感慨深いものがあります。
・当イベントでは、受講者は「浜松に関するアニメ企画」という縛りでの企画作りをしていますが、浜松に限らず、藤津さんの考える作品における(制作やコンテンツツーリズム、または単純に舞台として、など広い意味での)地方の持つ重要な要素はなんでしょうか?
藤津さん:日本の大半が「地方」であるのだから、もっと地方が舞台の作品があってもいいはず、とまず思っています。単なる「愛すべき故郷」としてだけでなく、犯罪も含めた事件の現場であることも含めて、もっと地方が舞台になったほうが自然でしょう。
アニメ制作の場合、ネットワークと宅配便の普及で、物理的な距離のデメリットは大幅に減っています。地方を拠点に元請けをするスタジオも着実に増えています。なので、浜松に縁がある人がいれば、浜松にスタジオができてもおかしくない状況だと思います。
「地方の持つ重要な要素」についてですが、作品の舞台としては、「日本に住む多くの人にとって身近な風景」であること、クリエイティブの現場としては、「生活コストが安く、環境がいいこと」があると思います。
・また、当イベントには「地方とアニメーション」という軸の他に「プロデューサー育成事業」という側面もあります。ご職業柄、今まで数多くのプロデューサーの方とお話をされてきたと思いますが、藤津さんの考えるプロデューサー像とはどんなものでしょうか?
藤津さん:「優秀なキャッチャー」です。ボールを投げるのはクリエイター=ピッチャーですが、必要に応じてピッチャーをリードしたり、ワイルドピッチになった時には体を張って受け止める存在。
・ちなみに、藤津さんは当イベントの顧問である赤尾さんとも面識があるようですが、お二人で共通するアニメに対する意見などはあったりするのでしょうか?
藤津さん:赤尾先生とアニメの好みについて語り合ったことがないので不明ですが、赤尾先生のほうが僕よりポップ指向が強く(広く楽しめるエンターテインメント性を重視する)、僕はもうちょっと風変わりな、不思議なテイストの作品を好んでいるのではないか、と勝手に想像しています。
・最後に、このA BloCreationという企画に対してのご意見をお願いいたします。
藤津さん:意義のある企画と思います。一つ付け加えると「PDの考える企画」と「クリエイターの考える企画」の違いが体感できると、もっとよいかなと思いました。
以上、藤津亮太さんへのインタビューでした。
藤津亮太さんもいらっしゃる企画発表イベントの詳細はこちらです。
見学のご応募もこちらのフォームより受け付けておりますので、みなさまぜひご来場ください。
Posted by ABC実行委員会 at 13:34│Comments(0)